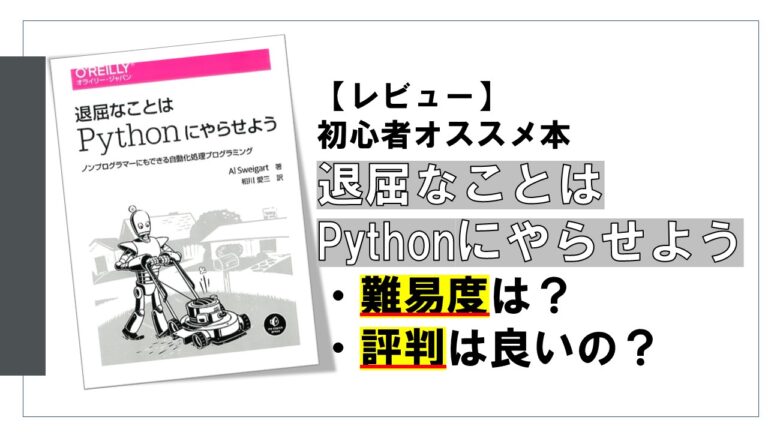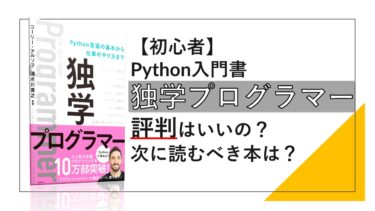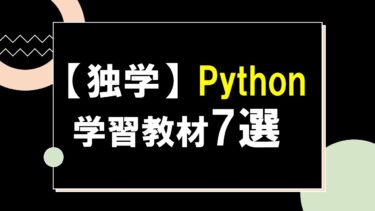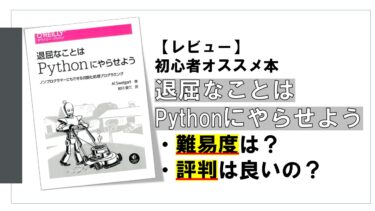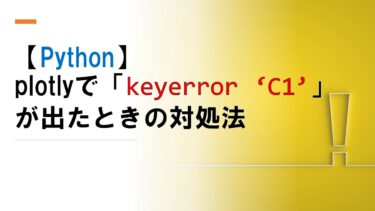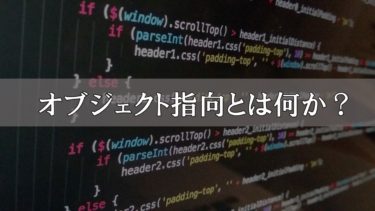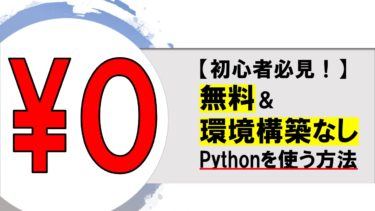こんにちは、今回は初心者向けのPython本として人気の「退屈なことはPythonにやらせよう」のレビューを行っていきたいと思います。
私もこの本でPythonを業務で使う方法を学ぶことができたので、仕事を効率的に行いたい人にはオススメできる1冊になっています。
この記事では
- 本の評判は良いの?
- 難易度はどれくらい?
- 読むときの注意点は?
などの疑問を解消していきたいと思います。
2021年10月に第2版が発売予定でしたが、2022年7月27日に変更さています。(Amazon調べ)
英語版では2019年出版みたいなのですでに古い情報になっているかもしれません。
この本は「独学プログラマー」の後に読む本としても紹介しています。「独学プログラマー」の難易度や勉強法は以下の記事でまとめています。
こんにちは。皆さんはプログラミング学習にはどんな本を使ていますか? たくさんの本があってどれから使っていいのか迷ってしまうという人も多いと思います。 そこで、今回はプログラミングの入門書として有名な「独学プログラマー Pyth[…]
本の目次・構成

この本は2部構成になっています。Pythonの基本文法と自動化処理に分かれています。
※初版をもとにしています。
| 第1部 | 内容 | 第2章 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1章 | Python入門 | 7章 | 正規表現によるパターンマッチ |
| 2章 | フロー制御 | 8章 | ファイルの読み書き |
| 3章 | 関数 | 9章 | ファイルの管理 |
| 4章 | リスト | 10章 | デバッグ |
| 5章 | 辞書とデータ構造 | 11章 | Webスクレイピング |
| 6章 | 文字列操作 | 12章 | Excelシート |
| 13章 | PDFファイルとWord文書 | ||
| 14章 | CSVファイルと JSONデータ | ||
| 15章 | 時間制御、自動実行、プログラム起動 | ||
| 16章 | 電子メールやSMSの送信 | ||
| 17章 | 画像の操作 | ||
| 18章 | GUIオートメーションによるキーボードとマウスの制御 |
その他には付録A、B、C、Dがついており、演習問題の解答やインストール方法などの各章で共通する内容が書かれています。
また、各章でまとめと演習問題が必ず書かれているので腕試しにはもってこいですね。
当サイトでもPythonの基本文法を学ぶことができます。
Python初心者向けの文法のまとめ記事一覧です。 独学で勉強するための順番を紹介していきます。 Pythonは比較的文法が簡単なので初めてでも理解しやすいです。 まだPythonをよく知らない人向けの記事はコチラ […]
難易度や評判は?

高評価のポイント
Pythonで何ができるのかがわかる
一般事務にはオススメ
ネットの口コミ
この本のテーマが自動化処理なので事務職には役立つという評価があります。
最近ではPythonがAIで有名になったのですが、日々の仕事に役立つとわかることでプログラミングがより身近に感じられるかもしれません。
低評価のポイント
章によっては不親切な内容
超初心者向けの本ではない
ネットの口コミ
確かにパソコン初心者にはハードルが高いかもしれません。
ネットで検索すれば解決はできますが、インストールやファイルパスのことなどが分からないと不安ですね。
パソコンを使ったことがない、もしくはYouTubeやSNSにしか使わないのであればより簡単な本からスタートする方が安心だと思います。
難易度に関して
ズバリ、難しくありません!
「簡単です」と言っていないのがポイントですね。(笑)
この本は一貫して「~オブジェクトをに対して、○○メソッドを使う」という表現で書かれています。もし、オブジェクトという言葉を聞いたことがなければ戸惑ってしまうかもしれません。
ですが、自動化処理を学ぶ上では「オブジェクトとは何か」よりも「このコードはどんな挙動をするのか」の方が大事です。
ですから、テキストに出てきているコードを自分で書いてみたり演習問題を解いたりすることで、十分仕事に活用することができます。
この本では「オブジェクト指向」については書かれていません。「オブジェクトとは何か」や「オブジェクト指向型プログラミング」をしたいのであれば他の本を読む必要があります。
「独学プログラマー」でも初歩を解説してくれています。
オススメできる3つの理由
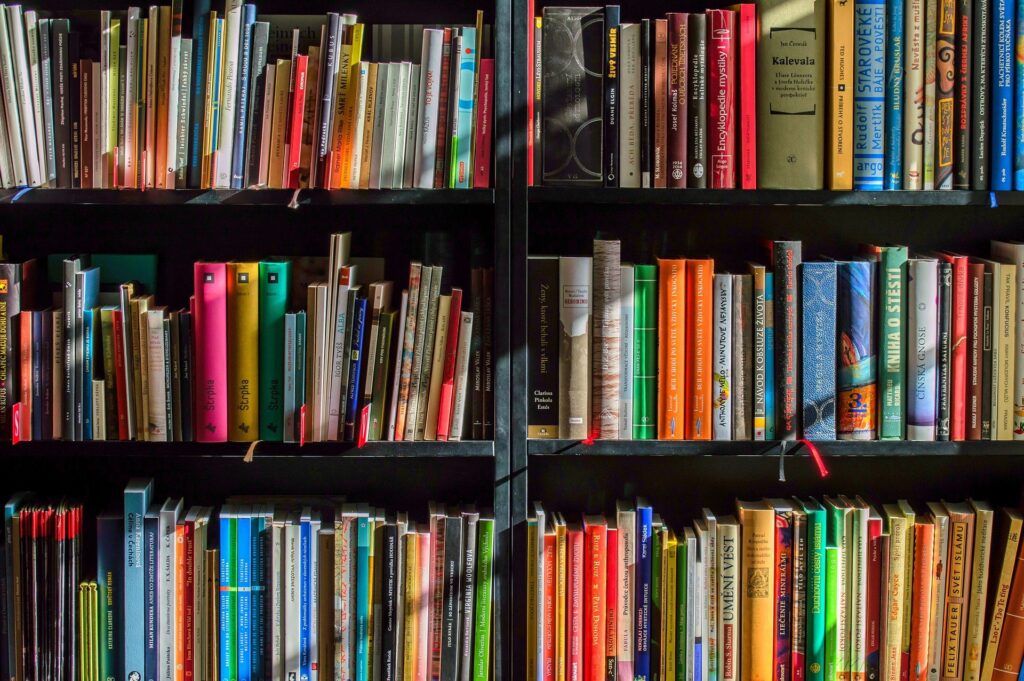
次におすすめポイントをみていきましょう。
- 演習問題が豊富で仕事につかえる
- 各章が独立しているので読みやすい
- 解説が統一されているので読みやすい
①演習問題が豊富で仕事につかえる
この本には各章の最後に演習問題がついています。また、章の中にもプロジェクトという形で業務にありそうな自動化処理の実例をいくつも紹介してくれています。
ただの解説書ではなく、タイトル通りの「いかにして自動化処理を使っていくか」をメインに書かれています。もちろん、関数やメソッドの紹介もあるので忘れたときに辞書として使えるのもポイント高いです。
たくさんの演習問題があるおかげで仕事への応用も考えやすいですね。コードを書くには頭を使う必要はありますが、完成すると超時短なのでメリットの方が大きいですね。
1枚ずつ作っていたプリントを
自動で大量に作成できました。
②各章が独立しているので読みやすい
第1部はPythonの基本文法なので初心者はすべて読むことをおススメしますが、それ以降の第2部は各章ごとに自動化処理を紹介しています。
前から読んでいかないと理解できないところも少ないので、必要なところだけ読むことができます。
特にExcelやWebスクレイピングは人気の内容だと思います。
大きなメリットですよね。
③解説が統一されているので読みやすい
これは個人的な理由ですが紹介しておきます。
先ほども書きましたが、この本のは一貫して「~オブジェクトをに対して、○○メソッドを使う」という説明がされています。
個人的には、このように同じ表現で説明が書かれているので理解しやすかったです。
オブジェクト指向に関しての直接的な説明はありませんが、なんども同じ表現で解説を読むことでオブジェクトとメソッドの関係を理解することができました。
これらの関係性を理解している人からすると当たり前かもしれませんが、当時の私は理解できてとっても感動していました。(笑)
注意点2つ

次に注意点の紹介です。扱っていない内容もあるので知りたい内容と合っているのか確認しておく必要があります。
- 分厚い本なので持ち運びには不向き
- オブジェクト指向に関しては書かれていない
分厚い本なので持ち運びには不向き
厚さは3cm弱なので持ち運びには不便だと思います。
残念なことに、Kindleでは英語版しか発売されていません。(2021年5月現在)
実際の大きさが気になる方は、書店で確認したほうが安心ですね。
オブジェクト指向に関しては書かれていない
この本の冒頭には
その場限りのコードを書く人向けの本なので、コードのスタイルや美しさにはあまり配慮していません。オブジェクト指向プログラミングやリストの内包表記、ジェネレーターなど、洗練されたプログラミングの考え方は、複雑になるので解説していません。
退屈なことはPythonにやらせよう
と書かれています。
プログラマーなら共同で開発することが多いためコードの読みやすさ(可読性)が求められますが、自分の仕事を自動化するだけなので、そういったところは書いていないということです。
もし、もっとシンプルなコードを書きたいとか、どんな変数名にしたらいいのか迷うのであれば「リーダブルコード」オススメします。
勉強方法は?
- 全部読まなくてもOK
- エラー対応は必須
全部読まなくてもOK
オススメ理由でも解説しましたが、この本の章は独立しているので必要な部分だけ読むことで最短で学ぶことができます。
第1部はPythonの基本文法なので初心者は読んでおいた方が安心ですね。
結局ほとんど読んでしまうんですよね。(笑)
公式サイトからは正誤表やサンプルコードを確認することができます。
初版ではコードが古くなっており警告が出るコードがありますが、正誤表で更新されているかもしれません。また、2021年10月には第2版が発売されます。
エラー対応は必須
プログラミング学習においてエラーの対応は避けて通れません。
たった1文字抜けているだけで動かなくなるのがプログラムです。煩わしく感じるかもしれませんが、警告文をそのまま検索すれば解決方法は出てくるのであきらめずに取り組みましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「退屈なことはPythonにやらせよう」のレビューを行いました。
分厚い本なので読む前に気力を失いそうですが、必要な部分だけを読むことで効率よく学習できる1冊になっています。
日々の業務を効率化したい人の参考になれば幸いです。
今回紹介した本では仕事の自動化がメインでしたが、プログラマーとして働きたい人向けの入門書として「独学プログラマー」がおススメです。
こんにちは。皆さんはプログラミング学習にはどんな本を使ていますか? たくさんの本があってどれから使っていいのか迷ってしまうという人も多いと思います。 そこで、今回はプログラミングの入門書として有名な「独学プログラマー Pyth[…]